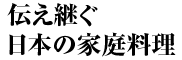「食べごと」なら農家に教えてもらおう
本誌『現代農業』の姉妹雑誌『うかたま』が、12月発行の冬号(49号)でリニューアルした。新しいコンセプトは「まるごと、食べごと。」
今から25年前、ちょうど『日本の食生活全集』が完結したときの「主張」の冒頭にこの「食べごと」という言葉が出てくる(1993年4月号)。「炭鉱あたりの女の人は、働いたあと“さあ、今から食べごとせにゃあならんもんな”とおっしゃるのね。料理しないといけない、ではなくて、食べごとをすると言うんです」。そんな、永らく炭鉱で暮らしてきた作家の森崎和江氏の発言を紹介しながら、「主張」はこう続く。
「さあ、食べごとせにゃあならん」と言って始めることは、まず共同の井戸への水汲みかもしれないし、売店への買出しかもしれない。農家ならば、屋敷うちの菜園へダイコンの一、二本を引きに行くことかもしれない。とすれば、そのダイコンの種まきもまた、食べごとの始まりといってよく、炭鉱の売店の共同運営のための寄合いですら、食べごとである。
それらが、まな板で菜を刻む響きや、炊き上がった飯の香りを生み、子が親に指示されて飯椀を供える仏前にもつながっていく。むろん食卓の談笑も、ときには「酒ごと」の喧嘩も、それらすべてが終わって食器を洗う指先の冷めたさも、みんな食べごと。食べごとの流れは無限につづく。……食べごとは、ときには「せにゃあならんもんな」の苦渋にもなり、ときには「食べごとせんか」と友呼びともなり、ときには「飯《まま》ごと」同様の遊びにもなる。ハレになりケになり、儀式になり、日常になり、遊びになる。
この懐かしさが漂う文章に、『うかたま』の若い編集者たちがビビッときた。かくしてリニューアル第1号の特集は「冬にやりたい 100の食べごと」。
「食べごと」なら農家に教えてもらおう、というわけで、農家が多く登場する特集になった。冒頭の「杵と臼でもちをつく」では千葉県の野口忠司さんから、初心者でもわかるもちつきの基本や、野口家定番のつきたてもちの食べ方――紫いももち、ヨモギもち、青のりもちなど見た目も味も楽しいアレンジもちをいろいろ教わった。産地の農家からは、ニンジン鍋、ダイコンまるごと一本を水のかわりに入れる雪見鍋、ヤマイモ団子鍋、セリ鍋など野菜が主役の鍋を教わった。本誌でニワトリへの飼料米利用の記事に登場いただいた山口県・(株)秋川牧園の佐藤尚志さんからは、ローストチキンの焼き方、切り分け方から鶏ガラ料理まで、ニワトリ1羽を丸ごと楽しむ方法を教えてもらった。また、ハクサイを漬けて57年、岐阜県の佐藤ユキヱさんからは、正月から3月まで、そのときどきでハクサイ漬けの味の違いを楽しむ知恵を教わった。
その他、ダイコンのいろんな干し方と食べ方、ミカン、ユズ、レモンなど冬の柑橘を丸ごと楽しむ工夫、さらには自作かまどのつくり方・使い方、正月かざりなどイナワラを編む方法まで、やってみたくなる「食べごと」があふれるにぎやかな特集になった。『うかたま』には都市の女性読者も多いが、おかげさまで評判はいい。
「食べごとの世界には、私たちが知らないこと、面白いことがまだまだありそう。たくさんのワクワクする食べごとを、みなさんと一緒に見つけていきたい」と、うかたま編集部は張り切っている。次号(春号)は「食べごと」のひとつとしてトマトのオモシロ栽培やイネの育て方も取り上げる予定だ。
食べごとの結晶をレシピ化して伝え継ぐ
昨年11月には、『伝え継ぐ 日本の家庭料理』(企画・編集 一社・日本調理科学会、以下『家庭料理』)の発行を開始した(「うかたま別冊」として全16冊発行)。
昭和初期の庶民の食を聞き書きした『日本の食生活全集』(全50巻)が「食べごと」の原典本、リニューアルした『うかたま』が食べごとの実用雑誌なら、この『家庭料理』は食べごとの結晶として昭和35年から45年までのあいだに定着した地域の味をレシピ化したシリーズ。『食生活全集』の実践版・実用的再現版だ。レシピの形で残すことで100年先まで伝え継ぐ。朝日、読売、毎日新聞や地方紙でも紹介され、おかげさまで順調にスタートできた。
第1回配本の「すし」に続き、第2回配本は「肉・豆腐・麩のおかず」(2月上旬発行)。魚介類を除いた、いわば「タンパク質のおかず」を扱った巻で、91品を、その料理への思いとともに掲載している。
肉ではニワトリが多く登場する。『うかたま』では先述のようにローストチキンで1羽丸ごと楽しむ方法を紹介したが、『家庭料理』のニワトリもまた丸ごと利用である。
「かつての農村部では、田植えや祭り、祝いごとなどのもてなしに自宅で飼っていた鶏をしめてすき焼きを楽しみました。大阪府の最北端に位置し、山あいに棚田が広がる能勢町では、秋は鍋の用意をして山へ松茸狩りに行き、炭火をいこして(おこして)、みなでゴザを敷いてとれたての松茸を入れたすき焼きを食べたりしたそうです。
鶏をつぶすと肝、砂ずり(砂肝)、玉ひも(内臓卵)などの内臓も出るので、それらも鍋に加えました。鶏以外の材料もそのときにとれる自家製の野菜や山のきのこなどが中心で、買ってくるものはほとんどありませんでした。
家でしめた鶏の肉はかためですが、噛んでいるうちにうま味とコクが出てきます。名古屋コーチンなどの銘柄鶏を飼っている人もあり、それをしめて食べるすき焼きはおいしさもひとしおです。1年ほど飼った鶏は黄色く味の濃い脂がしっかりつき、一般的なブロイラーの肉でも、その脂で炒りつけるとグンとおいしくなります」(大阪府「かしわのすき焼き」より)。
こんな食べ方もある。
「県の中央に位置する郡上市では2年寝かせた風味豊かな『地味噌』が土地の味で、漬物や調味料にもよく使われています。鶏《けい》ちゃんも地味噌を使ったたれに鶏肉を漬けこんで焼く料理です。昔は各家庭で地味噌をつくっていたので、味噌味の鶏ちゃんが一般的でした。今でもたれは自家製という人は多く、地味噌にしょうがやにんにく、果汁などを加えて深みを出した家庭ごとの工夫があります。(中略)もともとは、家で飼っていて、卵を産まなくなった廃鶏をつぶして食べたことから始まっており、盆や正月、親戚の集まりにつくられるごちそうでしたが、現在では週に1度というくらい頻繁に食べられるようになり、郡上の日常食になっています。味つけも味噌味だけでなく醤油味、塩味なども楽しむようになりました」(岐阜県「鶏ちゃん」より)。
ずっしり、ぎっしり、食べごたえのある豆腐
卵を産み続けて生を全うした親鶏だから、肉は固めだが味が濃く歯ごたえがあり、出汁がよく出て、モツや皮まで食べ甲斐がある。こうして命を無駄なくいただく。
豆腐も、こんな具合だ。
「ずっしり、ぎっしりと詰まった食べごたえのある堅豆腐が主役の煮物です。浄土真宗の祖である親鸞聖人の法要『報恩講』には欠かせない料理で、『殻しょ』とも書き五穀豊穣に感謝するものです。
山深い白山麓では焼畑で小麦、大麦、ひえ、粟、豆、芋などを栽培していました。冬は雪に閉ざされてしまうので、おもなたんぱく質源は手づくりの豆腐でした。栄養分の濃い豆腐で、にがりを多く使い、重しもきつくかけるので、縄で結わえてぶら下げて持ち歩くことができるほどかたいのです。1丁が700g以上もあるため、一度には食べきらず、生で食べたり汁物や煮物、田楽などにして食べました。そのため、なるべく日持ちがするように、傷みにくい冬につくられました。おからも、おかゆに入れて無駄なく食べたそうです。
今では豆腐店で買うことが多くなりましたが、店によって大豆の質、にがりの量、1丁の大きさなどに違いがあり、どの家も堅豆腐にはこだわりがあるので、どこで買うかは決まっているといいます」(石川県「こくしょ」より)。
この「肉・豆腐・麩のおかず」では、鶏のほかに豚(沖縄県のラフテー、スーチカー、豚足を使ったアシティビチ、ミミガーサシミなど)、牛(兵庫県のぐっだきなど)、羊(北海道のジンギスカン)、馬(青森県の馬肉鍋など)、いのしし(岡山県、島根県、徳島県、高知県のしし鍋など)、さらにクジラ(秋田県のくじらかやき、千葉県の甘煮、和歌山県の竜田揚げ、長崎県のくじらなますなど)、昆虫(宮城県のイナゴの佃煮、愛知県・へぼ(クロスズメバチの幼虫)の佃煮など)、そして卵と牛乳、豆腐と高野豆腐とおから、麩の料理……食べごとの結晶にふさわしいこだわりの料理が並ぶ。そのこだわりは「食べごと」の豊かな広がりへとつながっていく。
イチからつくって、うしろにある世界が見えてくる
そんな食べごとの世界が現代では、とりわけ都会ではすっかりちぢこまり、素材やそれを生み出す自然や人々のことに思いを馳せることも少なくなった。
生活に欠かせない食べものや衣料、生活用品などが、どのようにしてできるのか、素朴な疑問とまともに向き合い、見えにくくなった生産の世界やそれを支える人びとの営みに気づき、自然や社会、世界を見つめ直してほしい。
そんな子どもたちへの思いを込めて、農文協では絵本「イチからつくる」シリーズの発行を開始した。『カレーライス』『チョコレート』『ワタの糸と布』、いずれも海外からの輸入に多くを依存しているが、それをイチからつくってみる。
『イチからつくるチョコレート』の編者はAPLA(あぷら)とオルター・トレード・ジャパン(ATJ)。前者はフィリピン、東ティモール、インドネシアなどで持続可能な地域づくりのサポートをするNPO法人、後者はマスコバド糖、バナナ、コーヒー、カカオなど、食べものの交易を通じて、生産者と消費者の顔と顔がみえる関係づくりをめざしている会社だ。
絵本は、チョコレートの値段が製品によってなぜこんなに違うのかと疑問に思った少女が、「チョコレートのことを調べて、自分でチョコレートをつくるぞ!」と思いたつ場面から始まり、原料のカカオや農園での栽培のようす、カカオ豆を発酵、乾燥させて原料(カカオマス)になっていく過程を追い、市販のカカオマスでチョコレートをつくる方法を紹介。そしてこんな文章でしめくくっている。
「チョコレートを自分でつくってみると、チョコレートのうしろにある、別の世界がみえてきました。
イチから、自分でつくったチョコレートは、素朴で力強く、濃い香りのするおいしさでした。この手づくりチョコを食べたあとに、市販の安いチョコレートを食べると、それがまったく別の味と香りだということに気づきます。油脂と砂糖の味、そして人工的な香料の香りです。
それまで、わたしたちはカカオのほんとうの味と香りを知らなかったようです。
そして、チョコレートの値段が、安いものから高いものまである理由も、みえてきたように思います。
自分たちが食べるチョコレートの原材料には、何が使われているのか、どんな国の農家がどのようにカカオを育て、収穫したカカオは適正な価格で買いとられているのかどうか、そうしたことに目を向けないといけないのでしょう」。
本書の解説では、以下のように、カカオの生産国の状況にふれている。
日本で使用されているカカオ豆の大部分は、コートジボワール、ガーナ、インドネシアから輸入されたものだが、カカオ生産地 、とくに西アフリカでは、子どもたちが基礎教育も受けられずに、過酷で危険な仕事をさせられる「児童労働」が存在していることが、国際的な問題となっている。
「生産者が販売価格を決定できない不公平な貿易のしくみ」もある。カカオの国際市場価格は、商品先物取り引き市場で決まる。主要産地の作柄や病害虫被害、政治状況、需要と供給のバランスなどによってカカオの国際相場は変わり、また投資家たちによるマネーゲームによって、相場が乱高下することもめずらしくない。
こうした不公正な面をもつシステムを変えていこうという動きのひとつが「フェアトレード(公平な貿易)」で、この取り組みは、欧米を中心にアジアでも少しずつ広がりをみせている。
カカオを育てている人たちの中には、チョコレートを見たことも食べたこともない人もたくさんいるという。野川未央さん(APLA)、義村浩司さん(ATJ)は「あとがき」でこう書いている。
「つい最近とてもうれしいニュースがパプアの友人たちから届きました。自分たちが生産したカカオ豆でアイスクリームやチョコブラウニーを製造して、地元で販売を始めたというのです。つぎの夢は、村のカカオ生産者のおかあさんたちもいっしょにそうしたお菓子づくりをしていけるようになることだそうです。そんなパプアの友だちたちの夢の実現へ向けて、みなさんにも応援してもらえたらとてもうれしいです」(本号279ページもごらんください)
*
昨年12月、第72回国連総会で2019~2028年を「家族農業の10年」とすることが決定された(本号346ページ参照)。2014年の「国際家族農業年」を10年間延長し、一部の「育成すべき経営」に政策や予算を集中させるのではなく、世界で8割を占める小規模家族経営の生産基盤や生産条件を改善することを、国連は世界各国・地域に求めている。こうして飢餓をなくし、食料や環境問題を打開へと向かう。
2014年の「国際家族農業年」に関する国連・FAO報告(※)にはこう書かれている。
「おそらく、小規模農業を開発・支援する最も重要な理由は、小規模農業が多くの社会集団にとっての故郷だからである。こうした社会集団の解放は、より広範な社会や人間の開発にとっての鍵である」
故郷には食べごとの世界がある。カカオ生産者がカカオの「食べごと」化を豊かにすすめることを世界は願っている。
(農文協論説委員会)
『現代農業』2018年3月号「主張」
※報告書の邦訳本『人口・食料・資源・環境 家族農業が世界の未来を拓く 食料保障のための小規模農業への投資』(農文協刊)