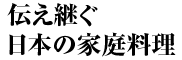おやつで思い出すふるさと
今年もお盆ではふだんは離れて住む子や孫の元気な顔を見ることができただろうか。迎える側としては、毎年変わらぬお盆の料理でもてなしたことだろう。
全国的に、お盆の前後には小麦を使った料理が多く食べられてきたようだ。昔から食べられてきた夏のおやつは、たとえば次のようなものだ。
・みょうがの葉焼き(宮城県)――小麦粉と砂糖、味噌を練った生地をミョウガの葉で包んで焼いた香ばしいおやつ。お盆には仏壇に供える。
・酒まんじゅう(神奈川県、山梨県)――夏祭りやお盆にはどこでも酒種から手づくりしていた。暑い時期のほうが発酵しやすい。
・おやき(長野県)――丸ナスに甘味噌をはさんだおやきは迎え盆、送り盆に欠かせない。
・みとりまんじゅう(福岡県)――「夏小豆」と呼ばれるみとり豆(在来のつるなしササゲ)のあんでつくるお盆のまんじゅう。
・炭酸まんじゅう(群馬県)――二百十日や十五夜のおやつ。お月見では子どもたちが家々をまわりまんじゅうを失敬するのが恒例行事だった。などなど……
もともとは、穫れ秋前で米の蓄えが減ってくるなか、ようやく収穫できた小麦を使って工夫されたもので、初夏から秋にかけての行事と結びついていることが多い。それが今ではなつかしい郷土の味になっている。
これらのおやつは、現在刊行中のシリーズ『伝え継ぐ 日本の家庭料理』の第3回配本『小麦・いも・豆のおやつ』で紹介されているもの。(一社)日本調理科学会という学会に所属する約360人の研究者が全国で地元の味を習い、いわれやならわしとともに、実際につくれるレシピ89品をまとめている。
つくりたいものがいっぱいでワクワク
寄せられる読者カードの反応はさまざまだ。愛知県の「じょじょ切り(太めで短い手打ち麺が小豆を甘く煮た汁に入ったおやつ)」を見た宮崎県の50代女性は「小豆あんは月に1~2回は炊くけど、これはなんだかしたことがない食べ方でワクワク」と書いてくれた。
香川県の高校教諭の40代の女性は、仲間にも見せたところ、男性も「柏餅はサルトリイバラ(主に西日本で柏餅を包むのに用いられる)でないといかん」などと、見るだけでお国自慢が始まったという。
岐阜県の50代の女性からは「待望の本が出たという喜びでいっぱいです。かんころもち(切ってゆで干ししたサツマイモともち米を搗いたもち)を長崎で探し求めたのを思い出しました。これほど、求めていた品が全部入っている本が出たことに感激」との感想をいただいた。職業は調理師とのことで、趣味としてだけでなく、仕事の上でも各地の郷土料理を知ることが役に立つのかもしれない。東京のある介護施設では、本シリーズや本誌の姉妹誌『うかたま』を参考に、デイサービスにやってくる認知症のお年寄りとともにいろいろな郷土料理をつくるプログラムを実施していて、来所者それぞれの技量を活かした作業をしながら、なつかしい味や知らなかった味を楽しんでもらっているという。
探しているものはここにある
いま子育て真っ最中の母親の間では、卵やバターが入らなくてもおいしいおやつが求められている。子どものアレルギーが多いので、できるだけシンプルで、もちろんおいしいものを食べさせたいという。そうした母親や、孫におやつをつくってあげたいおばあちゃん世代に人気の料理家が『うかたま』でも好評連載中の白崎裕子さんだ。「コンビニで冷凍うどんを買って来るより早くできておいしい地粉の即打ちうどん」や「米粉とじゃがいもでつくるショートパスタ『ニョッキ』」など、日本に昔からある素材で安心でおいしいレシピを提案し、単行本は全国の書店員と料理の専門家が選ぶ「料理レシピ本大賞」の大賞受賞や入賞を繰り返す実力派だ。その白崎さんが、『小麦・いも・豆のおやつ』を読んで「探しているものはここにある」と共感のコメントを寄せてくれた。
「ここに出てくるおやつはビジュアルと食感が違うだけで、じつは私のおやつの本のレシピとすごく近い。材料は一緒ですよ。地粉とか、昔から日本にある素材を使っています」
「(若いお母さんたちに)卵やバターが入っていない台湾のお菓子が人気です。もちろん台湾のお菓子はおいしいけれど、そもそも日本の昔のおやつには卵やバターが入っていない。台湾にはいもを使ったお菓子がいっぱいあるといわれているけれど、日本のほうがもっとあるってことにこの本を見ると気がつきます」
「限られた、数種類の材料がいろいろな形になり、地域によってつくる人によって、その人の手加減やさじ加減で変わる。いものだんごだけでもいっぱいあります。ゆでるの、蒸すの。ゆでるのだってつぶして粉を入れるの、冷めてからつぶすの、きりがありません」
「今、何を食べたらいいのか。私たちが一生懸命探しているものがこの本にあると思います。うちの子は卵アレルギーだからお煎餅しか食べられないという人がいたら、ここにあるよって教えてあげたい。でもそういうおやつがあることをみんな知りませんね。スーパーやコンビニには売ってないから」(『うかたま』52号「『日本の家庭料理』編集室から」より)
原型を残す作業と現代風の工夫で
みんなが知らなくなったものを、なんとか次世代に伝えたい。農山漁村でも知らない人が増えてきたが、それでも地域や家庭で今日まで引き継がれてきた食べものや料理がある。それらは、「私たちが一生懸命探しているもの」をはらんでいるにちがいない。そんな思いをもつ人たちが結集して、この『伝え継ぐ 日本の家庭料理』は成り立っている。
岡山県の笠岡市周辺に「ぶんずぜんざい」という緑豆を使ったおやつがある。ぶんず(緑豆)は傾斜地の流出を防ぐ、雑草を抑える、土を肥やすなどの理由でつくられてきたが、収穫は夏から秋の初めまでと長く、朝露がついている早朝に作業しないと、サヤがはじけて豆が散ってしまうので手のかかる「婆ごろし」といわれたという。一方で熱さましや化膿止めなどの薬効があると重宝され、なにより豆の味がよく砂糖が少なくてもおいしいといわれてきた。しかし小豆や砂糖が入手しやすくなると、ほとんどつくられなくなっていた。
そんな日本のなかでも珍しい、緑豆を利用する食文化を大事にしたいと考えたのが『伝え継ぐ 日本の家庭料理』の著作委員にもなっている地元岡山の山陽学園大学の藤井久美子先生。地域の生活文化の調査学習を進める中でぶんずのぜんざいに着目しているうちに、地元の人もそれほど興味を持たれるならと、地域のイベントでふるまったりするようになった。さらに、せっかく郷土のおやつをふるまうなら輸入ものでなく地元産の緑豆でつくろうという話になり、地域づくりのNPOが中心になって、わずかに栽培を続けていた農家からタネを分けてもらい栽培が始まった。
藤井先生は昔ながらの素朴なぜんざいのレシピを書き残す一方で、いまどきの学生に好まれそうな、ココナッツミルクと合わせた食べ方なども開発・提案している。ふるさとの食文化の原型を残す作業とともに、今風の新しい食べ方を工夫する試みを加え、栽培とともに次世代に伝えついでいく。
同様に、ドングリの食べ方を現代に伝え継いでいるのが、長野県王滝村で郷土料理の店「ひだみ」を営む瀬戸美恵子さん。「ひだみ」とはドングリのことだ。
もともとは救荒食・米の食いのばしとしてつくられてきたドングリの粉。ドングリといってもいろいろあるが、王滝村ではアクは強いが殻をむきやすいナラの実を利用してきたという。かつては粉を天日乾燥した特有の日なた臭さが美恵子さんも苦手だったというが、今は天日乾燥しないまま冷凍保存することで、どんな素材とも相性のよい粉になった。『小麦・いも・豆のおやつ』の巻ではその粉を使った昔ながらのひだみあんとひだみもちを紹介しているが、店ではドングリのパンやコーヒーゼリーも味わうことができる。
こうした、地域ならではの素材とその活かし方を受け継ぎながら新しい工夫も加えているのは、70~80代の先輩から地域の味を教わった50~60代の女性たちだ。その世代からさらに若い世代へと、地域の産物を再発見する楽しさを伝えていきたい。ちなみに、都市部の読者も多い『うかたま』52号では、街中でもできる「木の実拾い」のすすめをまとめている。
田畑の恵みと組み合わせて生きる海の幸
『伝え継ぐ 日本の家庭料理』の最新刊は第4回配本の『魚のおかず いわし・さばなど』。大衆魚と呼ばれたアジやサンマ、ブリやカツオにイカなど、全国の比較的広い範囲で食べられてきた魚と、そのときとれる魚でつくるすり身加工品、小エビを使った料理などが集まった(本シリーズでは、より地域性の強い魚や貝、川魚などを集めた『魚のおかず 地魚・貝・川魚など』も刊行予定)。
魚離れがいわれる昨今だが、日本人の魚の食べ方の豊かさがぎっしり詰まった1冊になった。おなじみの魚に意外な食べ方があるものだと感心する。
たとえば魚に添える薬味。ショウガとネギは全国的に使われているが、千葉県ではイワシと黒ゴマ、福島県や新潟県ではニシンとサンショウ、高知県では脂ののった刺身には葉ニンニクのペーストとユズ、福井県ではしめサバに辛子酢味噌といった具合に多彩だ。
魚とともに料理する野菜では、ダイコンが多彩な使われ方をしている。味のしみた厚めのダイコンがごちそうの富山県の「ぶり大根」。宮崎県では皮ごと粗くおろしたダイコンだけでイワシを煮た「すのしゅい」が体を温める一品だ。佐賀県の「いわしのかけ和え」は1本まるごとささがきにしたダイコンと酢漬けのイワシをゴマ酢味噌で和える。ダイコンがたっぷりで消化もよく胃にもたれない。茨城県からはイワシやサンマとダイコンを乳酸発酵させて骨までやわらかくした漬物「ごさい漬け」も紹介されている。
米と魚と発酵の妙
そして、魚と地域の農産物の組み合わせといえば、やはり米を使った料理になる。
小アジとご飯を2カ月ほど漬け込んだ石川県の「なれずし」は夏祭りのごちそう。しっかり重しをして乳酸発酵させたアジは身がしまって旨みが濃厚で「チーズのような味わい」でクセになる。岩手県の「かどのすし漬け」は生のニシンを内臓ごとご飯とこうじで漬けた冬場のごちそうで保存食。やはり乳酸発酵のさわやかさがおいしい。鳥取県の「するめの麹漬け」は、こうじ・野菜・するめそれぞれの甘みが重なったおいしさだ。
魚のヌカ漬け「へしこ」も福井県や岡山県から紹介されている。発酵により旨みが深まり「焼いた香りだけでご飯が食べられる」という。ヌカ漬けの魚をさらに酒粕で煮る石川県の「かぶし」や「べか鍋」、甘酒とともに野菜と漬ける「どぼ漬け」など、いろいろな状態の米と組み合わせた魚料理が食べられてきた。その魚と米の仲立ちをするのが発酵で、日本の気候風土を活かして1+1が3にも4にもなるおいしさを創り出してきたのだ。
やはり日本人は、魚があって米がたっぷり食べられることに幸せを感じてきたのだと再認識させられる。
農と漁が連携して地域の宝づくりを
『伝え継ぐ 日本の家庭料理』は刊行開始から1年がたち、これまでに『すし』『肉・豆腐・麩のおかず』『小麦・いも・豆のおやつ』『魚のおかず いわし・さばなど』の4冊を刊行してきた。次回は『野菜のおかず 秋から冬』を編集中だ(11月刊行予定)。
それぞれの料理を教えてくれているのは、各地の農協や漁協の女性部、生活改善グループや食生活改善推進員、農家レストランや加工所、民宿などで地域を盛り上げようとしている女性たちだ。誰もが野菜だけの専門家、魚だけの専門家というのではなく、地域の産物を丸ごと活かした地域の食文化という総合的な暮らしの知恵の継承者だ。
日本が世界に誇る「和食」のメインディッシュともいうべき魚食の文化もまた、地域の農産物と出会うことで豊かになった。そして、農と漁がつながると大きな魅力が生まれる。
日本一の売り上げを誇るという福岡県のJA糸島の産直市場「伊都菜彩」では、農産物だけでなく管内の漁協と連携して朝どれの新鮮な魚が並び、加工品や干物も人気だ。農協と漁協の連携で集客力は大きく高まり、年商100億円、年間来店者1000万人を実現している。一方、JAの資材購買店では、玄界灘産のカキを使った冬の風物詩「焼きカキ」の残渣のカキ殻で、シーライム(海の石灰)というオリジナル資材を開発・販売。農家や家庭園芸家に大変好評だ。ここでは畑と海がつながっている(2017年4月号の「主張」欄参照)。
折しも今年4月、協同組合の協議会だった「日本協同組合連絡協議会」が、一般社団法人として「日本協同組合連携機構」に生まれ変わった。どの協同組合もグローバリズム・規制緩和の攻勢を受けて厳しい状況に立たされているなかで、地域の課題に対し分野の異なる協同組合が制度・組織の垣根を越えて連携を強め、協同の力で組合員の暮らしを守っていこうという趣旨だ。農協、漁協、生協、森林組合などの連携で、子どもの居場所づくり、魚を増やす植樹運動、高齢者の仕事づくりなど、多彩な活動をめざしている。
「伝え継ぐ家庭料理」には人々をつなぐ力がある。家族のなかで、地域の行事や集まりのなかで大事にしてきたからこそ、伝え継がれてきた。そんな食がそなえるつなぐ力を活かすことで、協同の取り組みはより広く、より楽しくなるにちがいない。
(農文協論説委員会)
『現代農業』2018年10月号「主張」